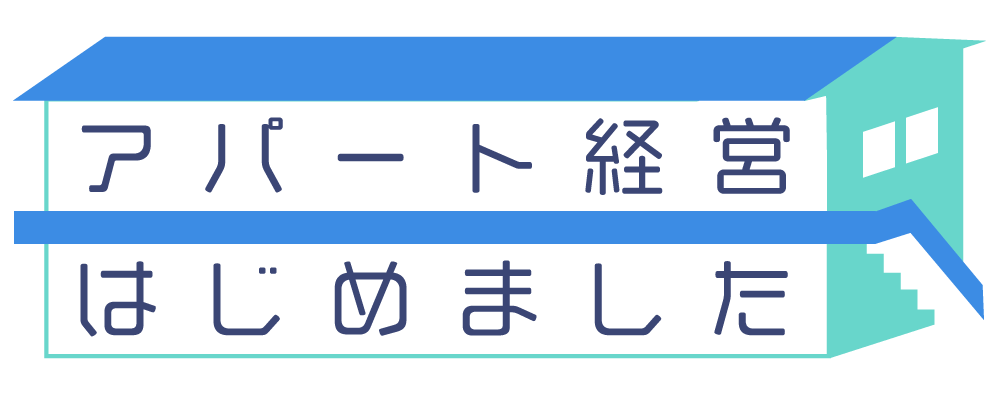「貯金はあるけど投資に回せていない」「時間はあるけど副業はできない」
「ただ収入は今より増やしたい」という公務員は多いはず。
私自身もフルタイム会社員のため副業OKではあるものの、限られた時間のなかで副収入を得るとしたら不動産投資だと判断し、不動産投資をやっています。
ただ公務員となると事情は少し変わるので、公務員でも不動産投資を副業としてバレずにできるのか紹介していきます。
公務員の副業規定と不動産投資の位置づけ
公務員は地方公務員法や国家公務員法によって「副業が原則禁止」されています。
なぜかというと、公務員が国や自治体など公共の利益を担う立場にあるため、公正さや公平性を守る必要があるためです。
具体的には、以下のような規定があります。
• 国家公務員法 第103条・第104条
公務員は職務に専念し、任命権者の許可なく他の事業や事務に従事してはならないと定められています。
• 地方公務員法 第38条
公務員は営利企業への従事が原則禁止されています。
例外的に許可が出る場合もありますが、許可なしでの副業は基本的にNGです。
では、不動産投資は副業に当たるのでしょうか?
実は、不動産投資は「営利目的の事業活動」と捉えられる場合と、そうでない場合があります。
大事なポイントとして「投資規模」と「運営形態」があります。
• 小規模で、自分が管理運営を行わない場合
一定の規模以下で、管理を不動産会社に委託している場合、営利企業への従事には該当しないと解釈され、問題ないと判断されるケースが多いです。
• 規模が大きく、事業的規模と判断される場合
アパート・マンション経営などで5棟10室以上(目安)を保有し、自分で積極的に管理運営を行っていると、営利企業従事と見なされる可能性があります。
つまり、公務員でも「規模を抑え、事業性を持たない形」であれば不動産投資は可能、とされているのが実態です。ただし、各自治体ごとに判断基準が異なるため、最終的には関係者に確認しておくのが無難でしょう。
公務員が不動産投資をしてもバレない理由・バレるリスク
公務員が不動産投資を始めるとき、「どうしたらバレないのか」「そもそもバレるリスクはどこにあるのか」という点は非常に気になりますよね。
まず、なぜ公務員の不動産投資がバレにくいのか、そして逆にどういう場合にバレるのかを整理します。
不動産投資がバレにくい理由
1. 所得税の申告情報が職場に直接届かない
家賃収入があっても、確定申告をきちんと行えば、国税庁(税務署)や自治体(市区町村役所)に提出するだけで、通常は職場(人事課)に情報がいくわけではありません。
2. 登記情報は基本的に外部に通知されない
不動産登記情報は公的なデータですが、任意で第三者が調べない限り、勤務先に直接通知されることはありません。
3. 副収入の情報は住民税の徴収方法次第
住民税を「普通徴収」にすれば、住民税の納付額が給与から天引きされず、自分で納める形になります。この方法を取ることで、副収入が勤務先に伝わるリスクを抑えられます。
バレるリスク
ただし、以下のようなパターンではバレる可能性が高まります。
1. 住民税の納付方法でバレる
副収入を得たまま「特別徴収(給料天引き)」を選んでいると、住民税額が通常より増え、その情報が給与担当部署に通知されます。これがきっかけで、「収入が増えている理由」を確認されるリスクがあります。
2. 不動産規模が大きく目立つ
アパートやマンションを複数棟経営し、大きな収益を得ている場合、登記簿で調査されたり、地元で噂になる可能性があります。管理業務を自分で行っている場合も「事業性が高い」と判断され、懲戒処分対象になるリスクが高まります。
3. 税務署から問い合わせがある場合
稀に、税務処理の過程で税務署から職場に問い合わせが入ることがあります。特に、申告内容に不備や疑義がある場合は要注意です。
不動産投資がバレないためにやるべき対策
公務員が不動産投資を行ううえで最大の懸念は「バレることによる職場での懲戒リスク」です。
実際に不動産投資を始めるにあたり、バレないように注意すべき具体的な対策を紹介します。
規模を大きくしすぎない
「5棟10室ルール」は、税務上の“事業的規模”を示す目安ですが、公務員にとってはこれが副業と判断されるラインでもあります。
そのため、戸建て1棟や区分マンション1室程度の小規模投資に抑えることが、グレーゾーンを避けるうえで安全です。
「管理を委託し、自分で業務をしない」「勤務時間外に不動産関連の行動を取らない」
ことを守ることで、自らが営利目的の事業に従事していると見なされるリスクを下げられます。
青色申告より白色申告を選ぶ
青色申告は節税効果が高い反面、事業性の証明にもなり得ます。
一方、白色申告は小規模投資家向けの形式で、事業性が低いと判断されやすいのが特徴です。
節税効果は弱くなりますが、節税よりも身を守ることが優先される場合、白色申告を選ぶことで副業として見なされにくくなります。
住民税の「普通徴収」を選択する
住民税の納付方法を「普通徴収(自分で支払う)」に変更することは、最も有効なバレ防止策です。
確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れることで、副収入が勤務先経由で処理されず、収入増がバレにくくなります。
ただし、税務署や自治体が処理を誤って「特別徴収」にするケースもあるため、申告後に市町村の税務課へ電話確認をするのが確実です。
不動産管理会社にすべて委託する
自ら入居者対応や管理業務を行うと、「自ら事業に関与している」と判断されやすくなります。
管理会社に全業務を外注することで、「ただの不動産オーナー」というスタンスを保ちやすくなります。
管理会社を使えば自宅に郵送物が届くリスクも抑えられ、家族や同僚にも気づかれにくくなるというメリットもあります。
これらの対策を徹底することで、公務員であっても不動産投資を安全に始めることが可能です。
公務員が不動産投資をするリスクとデメリット
公務員が不動産投資に興味を持つのは、安定した給与に加えて将来の資産形成を図りたいという理由が多いですが、一方で「副業禁止規定」という大きな制約があることも事実です。
次に、公務員が不動産投資を行うときのリスクとデメリットを具体的に解説します。
懲戒処分のリスク
最大のリスクは、副業禁止規定に違反したと判断された場合の懲戒処分です。
ケースによっては以下のような処分が下されることがあります。
• 戒告(注意)
• 減給
• 停職
• 最悪の場合は免職(懲戒解雇)
実際に、規模が大きくなりすぎた不動産投資が発覚して停職処分となった事例も報告されています。
「収益の有無」よりも、「どれだけ事業性があるか」が判断基準になるため、規模や運営方法に十分注意が必要です。
融資を受けにくい
公務員は信用力が高いため、個人向けの住宅ローンや少額融資では有利ですが、不動産投資となると話は別です。
金融機関によっては「公務員であること」を理由に副業としての不動産投資融資を渋る場合もあります。
また、融資申込時に勤務先や年収、職業内容を申告する必要があるため、審査過程で副業禁止職であることが伝わり、融資にマイナスに働くことはあるでしょう。
家賃滞納・空室リスク
不動産投資は「安定収入」というイメージがありますが、実際には以下のようなリスクがつきものです。
• 空室期間が長引く
• 入居者の家賃滞納
• 修繕費用が想定以上にかかる
• 自然災害や火災による損害
公務員は本業が忙しいこともあり、こうしたトラブル対応を迅速に行うことが難しいケースもあります。
不動産管理会社を使っていても、最終的な責任はオーナーにあるため、「放っておけば稼げる」という誤解は禁物です。
慎重に計画し合法的に副収入を得よう
公務員が不動産投資を行うことは、「副収入を得るための堅実な方法」として人気がありますが、法律や規則との兼ね合いが非常に重要です。
不動産投資そのものは違法ではありませんが、事業性の有無や運営方法によっては「副業」と見なされ、懲戒処分の対象になる可能性もあります。
・不動産投資会社に依頼し、業務を任せていく
・事前に税理士や行政書士など専門家に相談する
・書類や証拠を残して、「自己判断で始めた副業ではない」と示せる体制をつくる
といったことは意識するといいでしょう。
実働が少ない不動産投資は公務員でも挑戦しやすい副業ですので、興味がある方はぜひ挑戦してみてください。